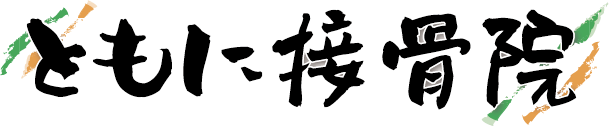スポーツ外傷とは
練習や試合中の衝撃や捻る動作で、筋肉や骨、関節などに急に起こるケガを総称してスポーツ外傷と呼びます。痛みの場所や発生状況を手掛かりに種類を見極め、適切に応急処置を行うことが回復を左右します。無理を続けると悪化しやすいため、早めの判断が大切です。
主なスポーツ外傷の種類
種類ごとに原因と症状、対処のポイントを知っておくと、いざという時に落ち着いて行動できます。ここでは頻度が高く、初心者から上級者まで起こりやすい外傷を中心に解説します。競技特性によって起こりやすい部位が異なる点にも注意しましょう。
捻挫
足首や手首などの関節が可動範囲を超えて捻られ、靭帯が伸びたり切れたりするケガです。腫れや熱感、体重をかけた時の鋭い痛みが特徴で、初期は安静と冷却で腫れを抑えます。
肉離れ(筋損傷)
ダッシュやジャンプの瞬間に筋繊維が部分的に断裂します。ふくらはぎや太もも裏に多く、ぶちっと切れたような感覚や内出血を伴います。固定と圧迫で悪化を防ぎ、復帰は痛みゼロと可動域回復が目安です。
打撲
転倒や衝突で軟部組織が傷つき、腫れや青あざが生じます。安静と冷却で早期対応すれば多くは軽快しますが、深部の骨や臓器損傷が疑われる強い痛みや吐き気を伴う場合は受診します。
骨折・疲労骨折
強い外力での骨折に加え、繰り返しの負荷で生じる疲労骨折も代表的です。押すと限局した痛みが続き、運動で悪化します。自己判断でのマッサージは禁物で、早期の画像検査が有効です。
脱臼
肩や指で多く、関節面が外れて激しい痛みと変形を伴います。無理に戻すと周囲組織を傷つけるため、固定して医療機関で整復を受けるのが安全です。
腱炎・靭帯損傷
ラケットやボール競技に多く、使い過ぎやフォームの乱れが誘因です。鈍い痛みから始まり、放置すると慢性化します。炎症期は休養を取り、再開時は負荷量を段階的に上げます。
脳震盪
頭部への衝撃で一過性の意識障害や吐き気、頭痛が起こります。症状が軽くてもその日はプレーに復帰しないのが原則で、経過観察と医療機関での評価が重要です。
初期対応と受診の目安
現場では「POLICE(保護・最適な負荷・冷却・圧迫・挙上)」が基本です。痛みを無視して動くと出血や腫脹が増え、回復が遅れます。数日で改善しない、しびれや明らかな変形がある、荷重不可、夜間痛が強い場合は早期受診を。
応急処置のコツ
アイスパックは15〜20分を目安に間隔を空けて繰り返します。圧迫は血流を完全に止めない程度に調整し、心臓より高く挙上します。固定材がなければタオルや伸縮包帯でも代用可能です。
再開判断
痛みゼロ、可動域と筋力が左右差なく、競技特有の動作テストに合格してから段階的に復帰します。焦りは再発の最大要因なので、練習量は三段階(軽負荷→中負荷→試合強度)で上げましょう。
予防と再発防止のポイント
柔軟性と筋力のバランス、フォームの見直し、睡眠と栄養の確保が基本です。特に着地や切り返しの動作はケガの分岐点。ウォームアップでは心拍を上げてから競技特異的ドリルへ移行し、クールダウンで可動域を取り戻す習慣をつけると、外傷の発生率と重症化リスクを下げられます。